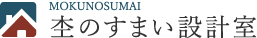- トップページ
- 施工風景詳細
山やまを望む家 ~土壁練り~
2025.9.13 (土)
このすまいで使う荒壁の土壁練りを行いました。
簑原さんと簑原さんの愛弟子のとも君は一足先に昨日から練る作業をしていたようです。
9月半ばで朝晩は少し涼しくなったとはいえ、残暑厳しい中の土練り&土踏みは重労働です。
お施主さまも朝から駆けつけてくださり、土踏みをしてくださいました。
ユンボであらかた土と水を練った後、藁を入れて裸足で土と藁と水を足指を使って踏みながら馴染ませていくのだそうです。
ユンボやミキサー、耕運機などで混ぜることもありますが、足で踏む作業は土と馴染みがよいそうです。
(感覚でわかるのですね)
藁切も藁切カッターではなく、昔ながらの藁切(押切)で手作業で切っていきました。
私も微力ながら藁切のお手伝いをさせてもらいました。この藁切も簡単そうでコツがあるのです。
簑原さんの顔の広さはもとより、由布市には除草剤を使わず、無農薬・無化学肥料でお米を作っている農家さんが多く
掛け干しもするので良質な藁が手に入るそうです。
こういった藁を使って土を練ると発酵の具合もすごく良いのだろうなと思います。
漬物やパン酵母を作る時も自然栽培の野菜や有機の粉を使うと元気に発酵すると聞いたことがあります。
土壁づくりにおいても同じことが言えるような気がします。
以前、これらの藁で土壁を練った時、準絶滅危惧種であるホウネンエビが生まれたという興味深い話も聞きました。
土壁に使う赤土(粘土)を使い始めた経緯や、土壁プールのつくり方、赤土の粒度バランス、藁を入れる量などを簑原さんから聞きながら
また一つ勉強になりました。藁はやはりとにかくたくさん入れるんだそうです。練り上りは感覚でわかると。。。
練った壁土はこの後、数カ月寝かせて藁を発酵させてから使用します。しばらく暑さも続きますのでよく発酵すると思います。
私のお義父さんは今現在は水車大工ですが、昔は建築大工でした。その父が言うには
「土は裸足で踏まにゃならん。それが弟子の仕事やった」とのこと。
土と馴染ませるという意味と人の常在菌を入れるという意味の2つあるのかなと理解しています。
味噌づくりにおいて素手で仕込むのがよいと言われる所以に通じるところがあるのではと。
よく、仕込む人や家によって味噌の味が変わると言うのは、常在菌の作用だそうです。
そう思うとお施主さま自ら素足で踏んでくれた土壁。
大変お疲れになったことと思いますが
「踏むのは楽しかったですよ」とおっしゃってくださいました。
土壁塗りが楽しみですね。